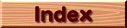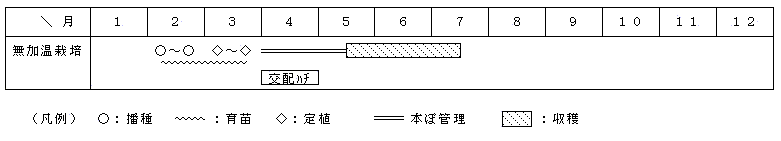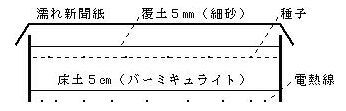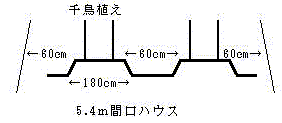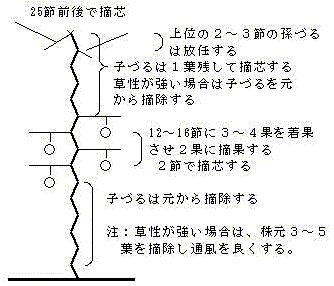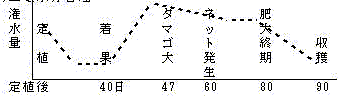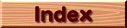

半促成アムスメロン
1. 品種 アムスメロン
メロンとしては多湿・多肥に鈍感で、つるぼけしにく い。うどんこ病やその他の病気にも強く、作りやすい。
糖度等食味が安定し、消費者に根強い人気がある。
2. 目標収量 3,000 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
ほ場排水が重要であり、必要に応じて暗渠を埋設する。
生育初期は低温、後期は高温になるので適切な温度管理 と水管理により草勢をコントロールする。
4. 技術内容
(1) 育苗
① 用土の準備 (ポット用土)
田土1に対して完熟堆肥1を混合する。
堆肥の代わりにクンタンを混合しても良い。
用土はpH6.5前後、EC値 0.1以下を確認する。
施肥量は床土1m3あたりN,P,Kとも250〜300g程度。
速成床土作成例(1,000リットル当たり)
材料/肥料 |
量 |
無病の田土 |
500 リットル |
完熟堆肥 |
300 リットル |
もみがらクンタン |
200 リットル |
苦土石灰 |
1.0 kg |
過燐酸石灰 |
2.0 kg |
細粒868
|
2.5 kg
|
使用する1カ月以上前に調整しておく。床土は県防除 基準に基づき消毒する。臭化メチルで消毒する場合は石 灰混合の時期に注意する。
② たねまき
播種期 2月上旬〜下旬(定植の30日前)
播種量 2,000粒/1,000㎡(定植本数の1.2倍)
(ア)播種方法
催芽は30℃で24時間行う(2㎜程度発芽)。
播種床にはバーミキュライトを使用するとよい。
覆土は、川砂を使う(転び苗防止)。
前日より加温し30℃を保つ。
播種床は、事前に十分潅水し、条間6㎝、深さ5㎜の播 種溝を切り、3㎝間隔でまく。
播種溝に対して種子の長径が直角になるように播種す る(双葉を並行に出させるため)。
発芽までは濡れ新聞紙をかけ、トンネルをコモで覆い 保湿する。
播種床(育苗床)
濡れ新聞紙 覆土5㎜(細砂) 種子
(イ)播種後の管理
播種後は床温30℃前後に維持し、発芽後は28℃位に下 げ乾燥ぎみに管理する。
(ウ)鉢上げとその後の管理
播種後8〜10日後、双葉が展開した段階で12㎝ポットへ 鉢上げする。
移植する時はできるだけ根を切らないようにていねい に抜き取る。
また、根が直射日光や乾風当たって乾かないように注 意する。
鉢上げ時の潅水は床温よりやや高めの温水を用いて株 元が落ちつく程度の最小限とする。
電熱線温床の温度管理は
本葉2.5葉期まで:気温25〜28℃、地温20〜22℃、 本葉2.5葉期以降:地温18℃前後で徐々に順化させる。
(2) 本ぽ準備
① 本ぽ準備
ほ場は、耕土が深く有機質に富んでおり排水が良いこ とが重要である。
地温を上げるため、定植1週間前に充分にかん水した 後、ハウスにビニールをかけ、畝全面を古ビニールで覆 い保温に努める。
② 施肥例(kg/1,000㎡)
肥料名 |
成 分 |
基 肥 |
備 考 |
完熟堆肥 |
|
2,000 |
施肥量はEC値に
よって調整する。
0.6以下 全量
〜1.0 半量
1.5以上 石灰のみ
|
苦土消石灰 |
|
150 |
ようりん |
0-20-0 |
100 |
CDU化成 |
16-8-12 |
60 |
硫酸加里
|
0-0-50
|
10
|
連作により苦土欠が発生しやすいほ場では、施肥量を 調整する。
③ 畝立て、裁植密度(1,800株/1,000㎡ )
(3) 定植
畝幅180㎝に2条の千鳥植え、株間40㎝とする。
植え穴は、前日にあけ十分に潅水しておく。
定植は、温暖な日を選び地表の地温15℃以上であるこ とを確認する(温度を上げるため1週間前からハウスビ ニールをかけ保温しておく)。
浅植えとし株元に砂や鹿沼土をおいて株元からの病害 の発生を防ぐ。
(4) 灌水
ポットへは十分潅水(ぬるま湯を)してから定植し、 定植直後は潅水しないことが望ましい。
定植後は、速やかにトンネル被覆して保温に努める。
定植2日目にぬるま湯をかん水しその後はなるべくか ん水しない。乾燥でしおれるような場合は鉢土と周囲の 土が馴染む程度に潅水する。
(5) 温度管理
生育ステージ |
昼 間 |
最低夜間 |
定植〜着果 |
28〜30℃ |
11℃ |
〜ネット発生 |
28℃以下 |
13℃ |
〜ネット完了 |
30℃以下 |
14℃ |
〜収穫
|
30℃以下
|
14℃
|
(6) 整枝 < 立栽培1ツル2果どり整枝 >
誘引は、展開葉7〜8枚でつる先の高さを揃えて誘引を 始める。展開葉5枚頃から側枝を取り除き草勢を抑える。
また、子葉もこの時期に除去し、主枝摘芯までに本葉 1〜3葉を順次摘葉する。主枝は25節で摘芯する。
12〜16節に3〜4果着果させ、良形2果を残し他は摘 果する。結果枝は、2節を残して摘芯する。
(7) 着果促進(交配バチ)
定植後、30〜35日で開花が始まるので、結果枝を観察 し開花2日前頃より搬入する。
(8) 摘果と雄花除去
鶏卵大の頃、大きさの揃った2果を残し、他の果は摘 果する(大小があると揃わない)。やゝ楕円形をしたも のを残す。また、摘果とともに雄花も早めに除去する。
(9) 玉つり
果実の直形が7〜8㎝位から玉つりを始める。結果枝 が着果節より下がらないように注意する。
展開葉10枚頃から主枝摘芯まで葉緑部に若干溢水が見 られる程度の水分を保つ。開花〜着果までは潅水しない。 果実が鶏卵大〜初期肥大が始まるまで、潅水を再開す るが、一度に少量ずつ、回数を多くする。
果径が7〜8㎝から硬化が始まるので、潅水を徐々に 控える。ただし、乾燥しやすいほ場は極少量の潅水を続 け、茎葉が固くならないように管理する。
(11)収穫の目安
(ア) 結果枝の葉が枯れる
(イ) 果皮が黄緑色に変わる
(ウ) ヘタの周囲が黄化
(エ) ヘタの周囲に離層(ヒビ)が入る
収穫は、果温が低い朝方に行う。収穫予定日の2〜3 日前に糖度検査を行い、15度を目標にする。
(12)病害虫防除
黒点根腐病が大きな問題となっている。
対策は、(ア)連作しない、(イ)作期を前進させ6月末ま でに収穫する、(ウ) 1果採りにより生育後半の根への負 担を軽くする、等が有効策である。
その他、県の病害虫雑草防除基準に準じて行う。
(13)主な生理障害(原因と対策)
① 裂果
ネット発生始めと収穫直前に多い。表皮の硬化が強い 場合、土壌水分の急増による急激な肥大によって花痕部 近くが大きく開裂する。暗渠による排水対策など地下水 位の影響を少なくする。
② 扁平果
ネット発生始めまでの肥大を抑え、後半になって急激 に肥大させた場合に発生しやすい。
着果後から硬化期までの過乾燥に注意し、茎葉がかた くならないように水分管理する。
③ 苦味果
昼間の温度が高く過乾燥や窒素過多による過繁茂状態 が続くと発生しやすい。
(松井 賢一)