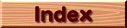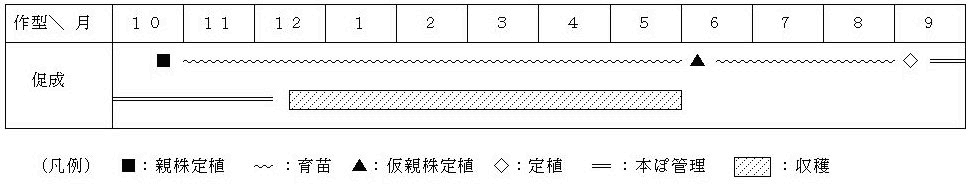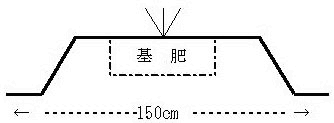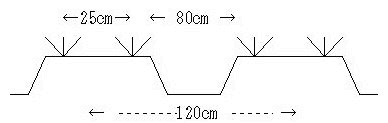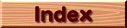

促成イチゴ
1. 品種 女峰、章姫
2. 目標収量 4,000kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
炭そ病を本ぽへ持ち込まないよう十分注意すること。
4. 技術内容
(1) 無仮植育苗
① 親株定植
前年の10〜11月に本ぽ 1,000㎡当たりウイルスフリー 苗100株を、畝巾1.5mの畝の中央に株間40㎝で定植する。 4月に入れば白寒冷紗(#300)で被覆するとともに、殺虫剤(粒剤)を畝全面に散布しておく。
② 無仮植育苗床施肥例 (㎏/60㎡,100株)
|
肥 料 名 |
成 分 | 基 肥 |
|
苦 土 石 灰 | | 7.0 |
|
よ う り ん |
0-20-0 | 2.7 |
|
普 通 化 成 |
8-6-8 | 2.0 |
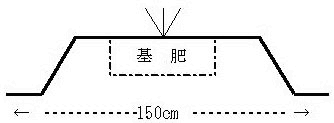
③ 仮親株定植
6月上〜中旬に親株から発生した第一子苗(太郎苗)を本ぽ1,000㎡当たり500株、畝巾2.0mの畝の片側に株間 40㎝で定植する。
根がよく発達した苗を選び、根を乾かさないようにすぐ植える。深植えしないこと。第一子苗から発生してい るランナーは取り除いておく。植え付け後は十分潅水し、活着までは潅水を怠らないこと。
④ 仮植床施肥例(㎏/400㎡,500株)
| 肥料名 |
成分 | 基肥 |
| 苦土石灰 | | 40 |
| ようりん |
0-20-0 | 15 |
| 普通化成 |
8-6-8 | 15 |

⑤ 仮親株の管理
発生するランナーは早めに摘除する(7/15まで)。
葉かきは古葉をとる程度とする。
樹勢が弱ければ、7月上旬までに普通化成を1㎏/100㎡程度株元に施用する。
⑥ ランナーの整理
7月中旬に行う。
長さ10㎝以上に伸びたランナ−はすべて摘除し、これ以降に発生した子苗を育てる。
高温乾燥期に入るので、潅水に注意してランナーの発生を促す(ランナー整理後一週間は特に大切)。
ランナーが重ならないように発根前に先端を誘導し、固定する。育苗後期の潅水は控える。
仮親株一株当たり20本の苗を目標とする。
⑦ 寒冷紗被覆(7月中旬〜8月下旬)
ほ場の乾燥防止とランナーの発生助長、炭そ病予防のため、白寒冷紗をトンネル状に被覆する。
(2) 本ぽ準備
① 太陽熱土壌消毒
梅雨明け後から約1カ月間行う。
1,000㎡当たり、切りわらを1,000㎏、石灰窒素を50〜100㎏施用する。
なるべく深くすき込み、畝巾60〜70㎝、高さ20〜30㎝の畝を立てる。
透明のポリフィルムまたはビニールで完全にマルチを行う。フィルム下に水を流し入れ、畝間に一時湛水して、ハウスを完全に密閉する。
② 施肥例 (㎏/1,000㎡)
| 肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 |
追 肥 |
| 苦 土 石 灰 | | 100 | |
| よ う り ん |
0-20-0 | 20 | |
| 有 機 配 合 |
5-5-5 | 300 | |
| 液 肥 |
12-5-7 | |
8×4回 |
③畝立て、裁植密度(9,200株/1,000㎡ )
(3) 定植
① 定植時期 9月5〜10日
② 苗の大きさ 本葉2.5〜4.5枚
③ 裁植密度 株間18㎝
④ 定植の方法
大苗、中苗、小苗の3つに苗を分けて揃えて植える。 植える時は根を乾かさないよう、苗を取ったトレイに濡れた新聞紙をかぶせる等注意する。
着果方向を揃え、クラウンの半分程度が埋まるように浅植えする。
(4) 潅水
活着するまでは十分潅水する(一回の潅水量は少なく、回数を多く)。
活着後は畝を乾かさないように、葉水程度で少量多回数の潅水を行う。
(5) ハウス被覆と保温開始
花芽分化確認約1カ月後(10月20日頃)にハウスにビニルを被覆する。
最低気温が12℃以下になったら、ハウスサイドを閉め,
保温を始める。
11月上旬から夜間は内張りカーテンによる保温をする。
(6)換気
カーテンによる保温を始めるとハウス内の湿度が高くな る。湿度が高く株が濡れているときは、朝10〜15分間ハ ウスサイドを開けて換気を行う。
(7)温度管理
|
生 育 ス テ − ジ | 昼 | 夜 |
|
保温開始〜頂花房出蕾期 |
26〜27℃ | 12℃ |
|
頂花房出蕾期〜開花期 |
26〜27℃ | 10℃ |
|
開花期〜収穫期 |
23〜25℃ | 5℃ |
冬期の夜間は最低気温5℃を確保することは難しいが、0℃以下にならなければ大きな問題はない。
(8) マルチ張り
ハウス被覆後すぐに行うが、マルチを張る前に十分潅水しておく。
湿度を保つために畝間は開けておく。
(9) 交配
11月中旬頃の開花が始まったら早朝か夕方にミツバチを導入する。1棟1群(1箱、巣板3枚)で、1,000㎡まで交配可能である。
ミツバチ導入までに病害虫防除をしておくが、殺菌・殺虫剤の散布に対するミツバチへの影響期間はそれぞれの薬剤により違うので注意する。
(10)芽かき
保温開始時に頂芽1本とし、頂花房開花始めに頂芽とその直下のえき芽2本に整理する。
収穫開始以降は、常に2果房程度に管理する。
ランナーも除去する。
(11)下葉かき
老化葉や黄化した葉を株元からかき取る。
収穫期以降は株づかれ、病気、不授精果防止のため、老化葉を順次除去すが、新葉の発生が少ない時期なので、下葉をかきすぎないように注意する。
1株当たり1回1〜2葉とし、急激な葉かきは避ける。
次の果房の肥大を良くするため、収穫が終わった果房は早めに除去する。
(12)追肥
樹勢や葉色を見ながら行う。
液肥で1回当たり窒素成分1㎏/1,000㎡を施用する。
(13)電照による補光
樹勢が衰えてきた場合に樹勢維持のために行うとよい。
日の出前の2〜3時間の連続電照、もしくは夜間中、1時間に5分程度の間欠電照を行う。
(14)主な生理障害
① 頂部軟質果
(ア)原因
密植(日照不足)、多湿、低温で発生しやすい。
(イ)対策
果実に光が良く当たるよう下葉かきを徹底する。
天気の良い日は換気を行ってハウス内の湿度を下げる。
潅水を控える。保温に努め、昼間の温度管理を高めにする。
② 奇形果
(ア)原因
窒素過多、日照不足、多湿、低温で発生しやすい。
(イ)対策
(15)その他
収穫後期の糖度低下
①原因
成り疲れによる樹勢の低下
高温による成熟日数の短縮
②対策
頂果房、一次えき果房の着果負担の軽減
株の活力を維持するため温度管理に注意するとともに、後半まで肥効を落とさないよう生育状況を見ながら追肥を行う。
(中川 浩志)