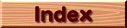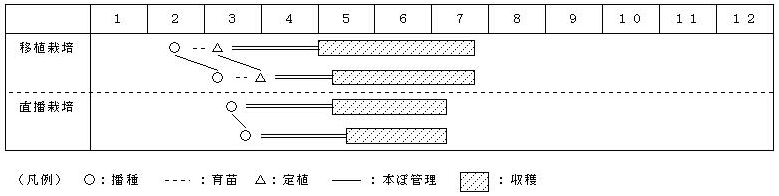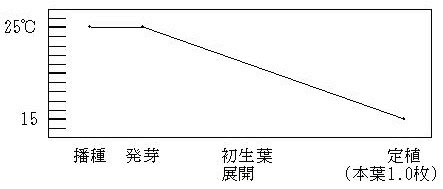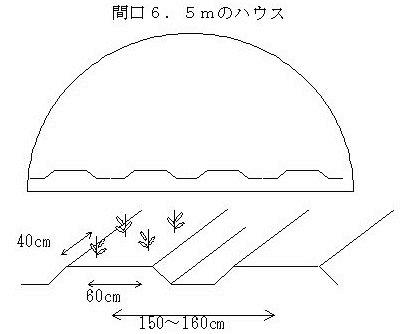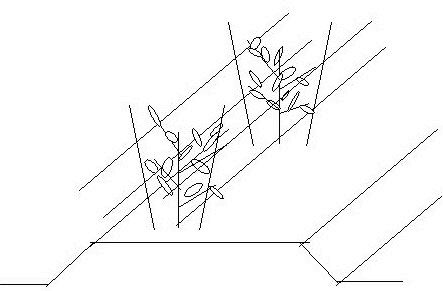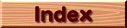

半促成サヤインゲン
1. 必要な施設条件
(1) ほ場条件
排水性と通気性が良く、耕土の深い肥沃な土地を好む。
(2) 施設 パイプハウス
2. 品種例
矮性種(つるなし)、半つる性種、つる性種がある。
関西市場では、矮性の丸莢の品種が好まれる。
(1) セレモニー
矮性種、すじ無し、丸莢の早生豊産種である。莢色は 濃緑、莢長は12cm程度で柔らかく曲がりが少ない。草丈 は50cm程度で播種後55日で収穫できる早生種である。
(2) ライトグリーン
矮性種、すじ無し、丸莢の早生豊産種である。莢長は 10〜12cm程度で、曲がりが少なく濃緑色で光沢がよい。
また、子実の膨らみがほとんどない。草丈は50〜55cmで 播種後55日前後で収穫できる早生種である。莢色はセレ モニーより濃緑である。
3. 作付体系例 半促成インゲン → 春菊
4. 目標収量 1,500kg/1,000㎡
5. 栽培のポイント
インゲンは比較的低温には強いが、10℃以下にならない よう特に春先の保温には注意する。逆に、夏期の高温は 落花、落莢、曲がり果を助長するので、換気に注意する。
また、収穫調整作業に手間を必要とするので、労働力 に見合った1回あたりの栽培面積の決定が必要である。
6. 技術内容
発芽温度は20〜30℃(最適温度23〜25℃)であるため、 低温期(2月中旬〜3月上旬)は温床育苗を行う。
3月中旬以降は、ハウスに直播が可能である。
(1) 育苗
① 育苗床の準備
1,000㎡当たり1.2m×7〜8mの床を作る。
電熱線は250W/3.3㎡準備し、外側ほど密に、中心部 ほど粗く配置する。その際、地面との間に籾殻等を入れ、 断熱層を作る。
育苗床には農ポリのトンネルを作り、トンネル上には 保温用のシートを掛ける。
② 播種準備
(ア)用土の準備
市販育苗培土を350リットル準備し、7.5cmポリポット (3500鉢/1,000㎡)に充填し、育苗床に並べておく。
(イ)種子の準備
1,000㎡当たり10,500粒(3〜4リットル)準備する。
③ 種まき
播種の2日前には十分に潅水し、地温が23〜25℃にな るように加温しておく。
1ポットに3粒播き、播種深は1cm程度とする。
播種 後に再度潅水し、発芽までは新聞紙等で被覆して おく。
④ 間引き
初生葉展開期(播種後10日頃)に、病斑のある株や生 育の遅れている株を間引き、健全株1本立ちとする。
育苗床を広げて、3〜4倍にずらす。
⑤ 育苗管理
(ア)温度管理
発芽最適温度は23〜25℃である。発芽後は軟弱徒長を 防止するため徐々に設定温度を下げ(下図)、定植の前 には15℃まで落とし定植後の環境に慣らしておく。
日中は30℃を越さないように換気に注意し、光に十分 に当ててやる。また、夜間は10℃を切らないよう、寒い 日にはコモ等で保温に注意する。
(イ)水分管理
発芽までは新聞紙被覆で乾燥防止するが、発芽後はい ち早く新聞紙を取り除く。その後の過潅水は軟弱徒長、 生育停滞、病害発生を助長するため、発芽後はポット内 の水分を控えていく。培土の表面が乾いてきたら潅水す る程度の管理を続ける。
(2) 本ぽの準備
① ほ場の選定
サヤインゲンは肥沃で排水性の良いほ場を好む。
エンドウのように強い連作障害は起こらないが、輪作 をする方が収量性は高い。
② 施肥
定植の1カ月前には完熟堆肥を、1週間前には基肥を 施し土とよくなじませておく。 また、サヤインゲンは塩類集積土壌や酸性土壌をきら うため、特に野菜の連作ハウスでは土壌分析に基づいた 施肥を行う(最適pH6.3〜6.5)。
追肥は5月の収穫始めの時期と6月の収穫盛期に実施 し、その後は樹勢を見て遅れずに行う。
施肥例 (kg/1000㎡)
肥 料 名
|
基肥 | 追 肥 |
|
収穫始め |
収穫盛期 |
適時 |
|
完熟堆肥 |
2、000 | | | |
| 有機石灰 | 100 | | | |
|
緩効性肥料 | 70 | | | |
|
BM苦土重焼燐 | 20 | | | |
|
速効性肥料 | 50 | 20 | 20 | 10 |
(N:15 P:19 K:14)
②畝立て、マルチング
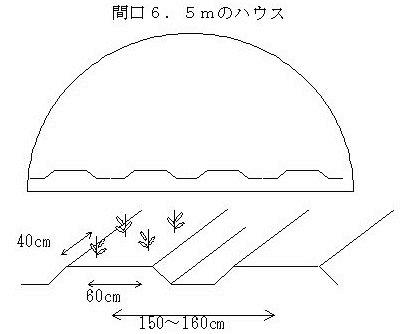
耕起の1週間前には十分潅水し、畝幅150〜160cmの畝 を立てる。インゲンは排水性の良いほ場を好むため、水 田など過湿土壌では高畝にした方がよい。畝立て後は速 やかにマルチをし、地温の確保に努める。
(3) 定植
本葉1枚時に、条間60cm、株間40cm、やゝ畝肩寄りに 2条千鳥植えし、3,300株/1000㎡を確保する。
なお、3月中旬以降に直播をする場合でも、上記の栽 植密度で1穴3粒播きとする。そして、初生葉展開期に 育苗時と同様に間引きを行う。
(4) 温度管理目標
生育ステージ |
昼温 |
夜温 |
目 的 |
生育初〜着花期 |
10℃ |
27℃ |
花芽分化、過繁茂防止 |
開花〜収穫期
|
15℃
|
27℃
|
受粉促進、落莢防止
|
10℃以下の低温ではほとんど生育を停止し、凍害で致 命的なダメージを受ける。定植(直播)以降、霜害の心 配が無くなるまで、ハウス内に農ポリまたは不織布によ るトンネルをし、保温に努める。
逆に高温限界は35℃で、30℃を越えると生育は阻害さ れる。開花、結実期に25℃を越えると、弱小花芽が増加 し、落花、落莢、異常莢の発生を助長する。
4月以降気温が上昇してきたら、日中の気温に気をつ け、限界温度を超えないように注意する。
(5) 支柱立て
株の倒伏による曲がり果の発生防止や果実の汚れ防止 のため支柱による支えをする。2m間隔に支柱をたて、 株をはさみこむようにひもを張る。ひもは生育に応じて 2段階の高さに張る。
(6) 潅水
乾燥条件では開花数の減少や落花が増加する。逆に過 湿条件では生育が極めて悪くなる。定期的な潅水に心が け、潅水チューブもしくは畝間潅水で行う。
(7) 摘葉
株の中心部に光を入れ、莢色を濃くし、新芽の発生を 促すため、定期的に古葉や混み合っている部分を摘葉す る。また、病害予防にもなる。
(8) 収穫
開花後10〜15日の若莢収穫につとめ、Mサイズ中心の 出荷をする。収穫遅れの莢を残しておくと株の負担にな り、収穫期の短縮にもつながるので注意する。
(9) 主な生理障害
① 落花、落莢
開花〜結実期に25℃を越える環境が続くと、落花、落 莢が多くなる。
換気および簡単な遮光が効果的である。
② 曲がり果
栄養不足や樹勢の弱りが原因である。また、株の倒伏 による物理的な要因もある。対策は、適切な追肥作業と 支柱立てによる倒伏防止が有効である。
(10)主な病害虫と防除
県病害虫防除指針に基づく。
(田中 寿 )