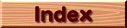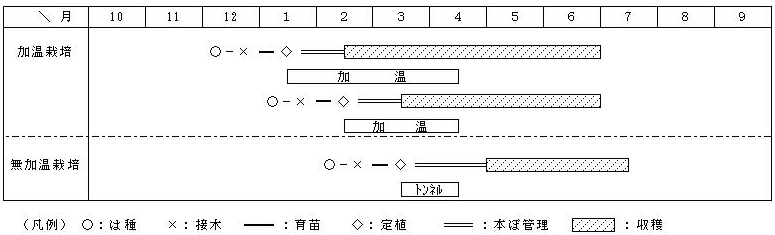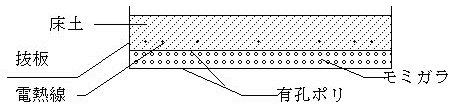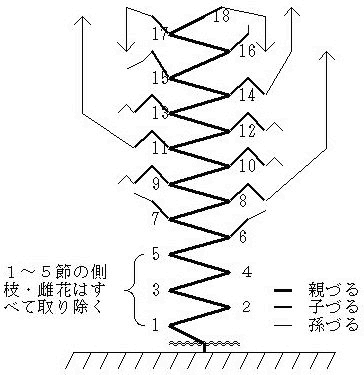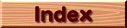

半促成キュウリ
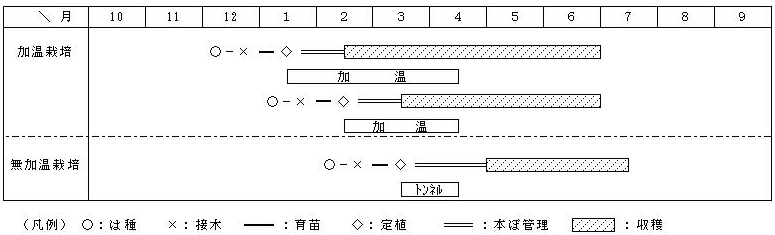
1. 品種例
(1)穂木
果実の光沢が良く果色の濃い品種を選定する。 長期穫りは草勢が後半まで安定している品種、短期穫り は初期から収量が安定している品種を選定する。
(長期穫り)アンコール8、シャープ301
(短期穫り)アンコール10、アルファ-節成
(2) 台木
土壌および栽培時期、栽培法に応じて、品種を選定し、 草勢を調節する。
強勢タイプ:Newス-パ-雲竜、エキサイト一輝、
ビッグパワー 持続タイプ:雲竜セブン、ゆうゆう一輝、
ハリケーン1号
2. 目標収量
16,000kg/1,000㎡(加温12月まき)
14,000kg/1,000㎡(加温1月まき)
10,000kg/1,000㎡(無加温栽培)
3. 栽培のポイント
(1) 加温12月まき栽培では、定植時期が厳寒期に当たり、最低地温18~20℃を確保するために地中加温装置(温湯暖房装置・電熱線)を必要とする。
また、二軸二層カーテンも必要である。
(2) 長期穫り栽培については、初期に温度を高くして収穫を急いだり、初期収量を高くし過ぎると根張りが悪くなり、後期まで草勢が維持できないので初期はやや抑え気味に管理する方が良い。
(3) 加温・保温時期の管理で、夕方における天窓・内カーテンを閉める温度および夜温の高低が栄養生長・生殖生長への分岐点となるので細心の注意を要する。
(4) 整枝は摘心・放任・摘葉を繰り返し組み合わせながら、
草勢を保つとともに太陽光線が新葉に十分当たるようにする。
4. 技術内容
(1) 育苗
① 床土の準備
12cmポットを使用する場合、ポット当たり 0.8リットルの鉢土が必要である。は種床を含めて1,000㎡当たり3m3 程度準備する。
(ア)熟成床土
使用する有機物は半年ぐらい前より雨ざらしにして塩分を十分に除き、使用する時期には完熟しているように土と交互に積んでおく。 未熟の有機物が混入していると育苗中にガスが発生して障害が出るので注意する。
熟成床土1,000リットル当たり
田土 500リットル
堆肥 400リットル
ピートモス 100リットル
苦土石灰 1kg
過りん酸石灰 2kg
細粒868 2kg
(イ)促成床土
床土は熟成したものを使用するのが望ましいが、手間がない場合は市販されている資材を配合しても良い。
促成床土 1,000リットル当たり
田土 500リットル
購入土(肥料入り)500リットル
苦土石灰 1kg
過りん酸石灰 1kg
細粒868 1kg
※ は種床土に使用する場合、熟成床土、促成床土
とも肥料は苦土石灰、過りん酸石灰のみとし、
細粒 868は施用しない方がよい。
② 床土の消毒
床土は臭化メチルで消毒する。臭化メチル1缶(500g)で2m3の用土が消毒できる。 石灰等のアルカリ肥料は消毒の数週間前あるいはガス抜き後施用する。
床土を高さ60cm程度に積み上げ、弓を張ってガスが床土全体に行き渡るようにする。ガスが噴出した時に直接床土に吸収されないように薬剤の缶を置くところにビニールを敷いておく。床土は全面ビニールで覆い、完全密閉してガスを噴出させる。
くん蒸期間は夏季3日間、冬期7~10日間を目安とする。地温5℃以上で使用する。
くん蒸後は十分にガス抜きして使用する。
③ 育苗施設
(ア)施設内の温度を保つため、内カーテンと加温機を準備する。また、接木作業場所および鉢上げ床への直射日光を避けるため、ラブシート、寒冷紗、遮光ネット等で遮 光する。
(イ)苗床は、は種床と移植床では必要面積や管理温度が異なるため、次のように組み立てる。
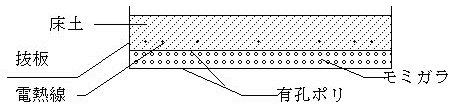
※ 電熱線は外側ほど狭く配置する。
1000㎡分の苗を育てるのに必要な苗床面積
穂木は種床 1.2× 2.5m 300W/3.3㎡
台木は種床 1.2× 4.0m 300W/3.3㎡
鉢上げ床 1.2×16.0m 150~200W/3.3㎡
④ 種子量(1,000㎡当たり)
穂木 1,600~1,800粒
台木 1,600~1,800粒
⑤ は種
台木品種や接木方法により穂木と台木のは種間隔が異なるので注意する(種子袋に記載されている)。
呼接ぎでは穂木と台木のは種間隔を長くするほど穂木の胚軸が太くなり接木が容易である。慣れてくれば穂木と台木のは種間隔を短くすればよい。 また、接木はひとり1日当たり400本(初心者300本)を目安として、は種量を調節する。 床土の厚さは穂木6~7cm、台木7~8cmとする。直接、苗床には種した方が地温が確保され発芽や生育がすぐれる。接木作業を効率よく行う目的で育苗箱を利用してもよい。
は種の2~3日前に床土にたっぷりかん水して、通電し、地温を高めておく。 穂木は5~6cm間隔の条まきで、5mm程度のまき溝をつけ、3~4cmの間隔では種する。
台木は7~8cm間隔の条まきで、3~4cm間隔では種する。
は種後、種子がかくれる程度に覆土する。その後キャプタン剤で全体が湿る程度にかん水し、新聞紙を敷くと発芽が揃う。 は種後、地温は昼夜とも28℃前後にする。
また、夜間は温度を確保するためにトンネルにコモなどで被覆する。7割程度の発芽をみたら新聞紙を取り除く。また、徒長を防ぐために地温を20℃位に下げる。
水分は徐々に控えるようにし、接木の2~3日前からは晴天日の午後にわずかにしおれる程度までかん水を控える方が接木の活着率が高くなる。
⑥ 接木
は種後9~10日で接木適期となる。穂木は本葉 0.5枚、台木も本葉 0.5枚で胚軸5~6cm程度である。胚軸の長さはかん水の量によって調節する。接木の1~2日前からかん水を控えて硬めの苗に仕上げる。
接木作業は、ハウス内をビニール等で仕切り、気温を18℃以上確保して行う。
台木は竹べら等で抜き取って、ピンセットや竹べら等で生長点を取り除く。この際、きれいに取り除かなければ後で伸長してくる。
次に穂木の大きさに応じて、切る位置を決め胚軸の上から下の方に向け長さ1cm程度、深さは胚軸の 1/2に達するように約30度の角度で切り下げる。
穂木は子葉の1cm程度下から上に向け長さ1cm程度、深さは胚軸の 2/3に達するように約30度の角度で切り上げる。
それぞれの切り口をかみ合わせ、接木クリップで穂木側から固定する。
接木苗を植えつけるポットは、2~3日前にたっぷりかん水し、通電し温めておく。植えつけの前または植えつけ時にキャプタン剤をかん水する。
植えつけの際は、後で切断しやすいように穂木と台木の株元を離して植える。
⑦ 接木後の管理
接木当日はビニールを密閉し地温、気温、湿度とも高めにする。日中は萎れを防ぐため、寒冷紗や遮光ネット等で遮光する。
接木2日目は極力光線を当てるようにする。ただし、萎れが強いようであれば晴天日の日中は遮光するとともに葉水を散布する。
接木3日目は晴天日の日中の高温時だけ遮光する。 また、萎れてもできるだけ我慢することが必要である。
接木4日目は遮光はほとんど不要。換気をして高温を抑える。地温、気温とも徐々に下げるようにする。
きゅうりの胚軸の切断は接木後8~10日後に行う。 きゅうりの胚軸を7~8日目にピンセットでつぶし、活着の状況を確認したら次の日の夕方に切断する。切断後、萎れた場合は葉水と遮光で調節する。
接木後の温度管理
接木後日数 |
0~2 |
3~4 |
5~7 |
8~定植 |
気温
|
最高 |
30℃ |
28℃ |
27℃ |
27℃ |
最低 |
22℃ |
20℃ |
19℃ |
18~13℃ |
地温
|
最高 |
28℃ |
27℃ |
26℃ |
26℃ |
最低
|
24℃
|
22℃
|
21℃
|
20~17℃
|
(2) 本ぽ
① 施肥例<加温長期穫り栽培> (kg/1,000㎡)
肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 |
追 肥 |
堆 肥 |
|
3,000 |
|
有機石灰 |
|
150 |
|
骨 粉 |
4-22-0 |
100 |
|
有機化成 |
6-6-6 |
150 |
|
油 か す |
5-2-1 |
200 |
|
緩効性肥料 |
10-10-10 |
100 |
|
有機化成 |
6-8-6 |
|
200 |
液 肥
|
6-8-4
|
|
15kg×15回
|
肥料は有機質を含んだ有効成分量の少ないものや緩効性肥料を使用する。
施用前に残効肥料を測定し、残存量に応じて基肥の施用量を調節する。
残効肥料がない場合、元肥として施用する量は、N30kg、P40kg、K30kg/1,000㎡を目安とする。 マグネシウム欠乏が発生しやすいほ場では、堆肥やカリの施用量を控えるともに、基肥にマグネシウム資材を 施用しておく。 堆肥や石灰、骨粉は定植1ヵ月前に施用し、残りの基肥は定植1週間前に施用し、畝立てを行う。
pHの特に低いほ場では、有機石灰の代わりに消石灰または生石灰を施用する。 追肥は、穴肥を施用すると長期にわたって徐々に肥効が発現するため栽培管理がやりやすい。肥料は有機質肥料を主体にし、根を痛めない時期および位置に施用する。
草勢が弱い場合は、主枝の摘芯前に追肥を施用して草勢の低下を防ぐ。
液肥による追肥は、主枝の果実の収穫直前から行い、草勢および収穫量に応じて施用の量と時期を調節する。
希釈割合は300~500倍で、かん水と兼ねて行う。1回 当たりの施用量は成分量で1~1.5kg/1000㎡ とし、3~7日に1回の割合で施用する。収穫量が少ない時は施用量を控え、根を休ませる。
表は、穴肥を施用する場合の例である。穴肥を施用しない場合は、液肥の施用量を多くしたり、畝肩や通路に速効性肥料を施す。
また、葉面散布剤(液肥)の利用により栄養生長と生殖生長の調節を行うこともある。
最終施肥は収穫終了2週間程度前とし、できるだけ残効肥料を残さないようにする。
② 畝立ておよび植え付け準備
生育初期は低温のため畝はできるだけ高畝にする。
また、加温長期穫栽培では定植時期が根が活動する最低地温を下回るため、温湯パイプや電熱線を地中10cm程度の所に配置し、定植の数日前から稼働させ、定植時に は地温18℃以上にしておく。
かん水設備は定植2~3日前までに設置し、十分かん水しておき、地温が下がらないよう定植前後にはかん水しない。
かん水設備の設置が終わったらマルチの被覆を行い、植穴を掘ってトンネルをかけ、定植までに十分地温を高めておく。
③ 定植
畝幅180~200cm、株間70~75cm、条間50~60cmの2条植えとする。
は種後30~35日、本葉3.0~3.5枚の若苗定植を行う。
土壌の関係で草勢が強くなりすぎるほ場では、やゝ大苗定植を行う。
定植は温暖な日を選び、深植えにならないよう植えつける。
植えつけ後は速やかにトンネルを被覆して保温する。 特に購入苗は硬めにつくられている場合が多いため、トンネル被覆により温度と湿度を高めることにより活着と生育を促進させる必要がある。
活着までは昼夜とも高温(気温:昼間30℃、夜間16℃、地温:昼間27℃、夜間20~22℃)・多湿に管理する。 また、晴天の日の午前中に 500倍程度の液肥かん水を
行うと活着が促進される。

④ 温度管理
(ア)定植から活着まで
地温20~22℃にして活着を促す。
気温;午前:24~25℃で内カーテンを少し開ける。 湿度を十分に保つため全開を避ける。
29~30℃で天窓を開ける。
午後:22~23℃で天窓を閉める。19~20℃で内カーテンを閉める。
夜間:夜温を15~16℃に維持して活着を促す。
活着後は本葉10枚位までに夜温を徐々に下げ12~13℃にする。
(イ)本葉9枚~15枚位まで
地温;地温を18~20℃にする。
気温;午前:23~24℃で内カーテンを開ける。
午前中は少し(30cm)開く程度とし湿度を確保する。午後は徐々に全開するようにする。天窓は27~28℃位から開け、あまり高温にしない。
午後:18~19℃で天窓を閉める。15~16℃で内カーテンを閉める。
夕方の天窓・カーテン閉めは高い温度で閉めると徒長を促し側枝の発生が鈍ったり病気の発生を助長することになる。
夜間:本葉10枚以降、前夜温を15~16℃、後夜温を11~12℃に下げる(変温管理には4段サーモを利用するとよい)。
(ウ)収穫開始後
地温;18℃にする。
気温;午前:23~24℃で内カーテンを開け、27~28℃で天窓を開ける。午前中はカーテンを全開にせず、湿度を保ち側枝の発生を促す。
午後:18~19℃で天窓を閉める。15~16℃で内カーテンを閉める。肥大中の果実が多く着果している場合は、天窓・内カーテンを閉める温度をやゝ高くして肥大を促進する。反対に果実が少ない場合は、閉める温度を低くして側枝を充実させる。 主枝の摘心前はやゝ温度を低くして側枝の発生を促す。
夜間:前夜温を15~16℃、後夜温を12~13℃とする。夕刻の温度管理と同様、着果状況に応じて果実を肥大させるのか、側枝を充実させるのか判断して行う。主枝の摘心前は低めの温度管理を行う。
※ 日中の天候が悪い日は、全体を通じて1~2℃低い管理を行う。特に夕方~夜の温度には注意する。
⑤ 土壌水分管理
活着までは、土壌水分を確保するとともに湿度を高める。定植後に多量にかん水すると地温を下げて活着が遅れるため、定植前に充分かん水しておく。
活着後はかん水を控え目にし、徒長を抑える。
雌花が数個開花してきたら、かん水を少し増やして肥大を促す。
(エ)1番果収穫後からかん水量を増やすようにし、定期的にかん水する。かん水は晴天日の午前中に行う。通路は、ほこりが立たない程度に湿っている状態がよい。乾いていれば、晴天日の午前中に通路散水を行い湿度を保つ。
⑥ 整枝・誘引・摘葉
(ア)活着後(本葉7~8枚)誘引を行う。草勢の弱い株や品種では5~6節、普通の生育をしている株や草勢の強い品種では4~5節までの側枝と雌花を早めに取り除く。
(イ)普通の生育をしているものでは5~7節、草勢の弱いもの(品種)では6~8節から着果させる。極端に草勢の弱い場合は、上段の雌花まで肥大が始まらない内に摘み取り草勢の回復を図る。
(ウ)台木・穂木の子葉は1番果が開花するころに取り除く。残しておくと、うどんこ病の発生源となる。
(エ)下位(地際から50cm程度)の子・孫づるは1節摘芯にする。2月に収穫の始まる作型では、中~上位の子づるも1節摘芯にすると初期収量はやや低くなるが、孫づるが安定して伸長するため総収量は高くなる。
(オ)中位の子づるは2節摘芯を基本とするが、子づるの発生が悪い場合には、摘芯しないで草勢の回復を図る。 この場合、放任する子づるは1~2本とする。子づるが発生してきたら、放任した子づるは摘芯する。また、放任した子づるが強すぎる場合(生長点から4節目位の雌花が開花していない)は摘芯する。
上位の子づる(摘芯直下2~3節)は1節摘芯とする。
(カ)摘心は、17~18節(地際から 1.5m位)で行う。摘芯位置が高すぎると、収穫や管理作業の時に畝肩を踏んで生育に支障をきたしたり、上位から発生した子づるに十分に農薬がかからないため、病害の発生につながる。 この際、3枚程度展開している子づるが2本程度発生していることを確認してから摘芯する。
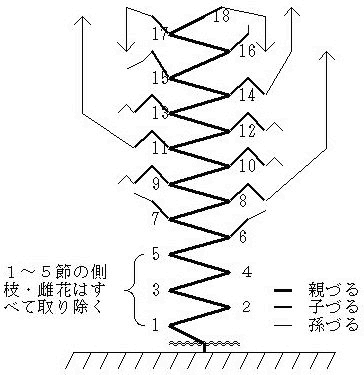
(キ)主枝の摘芯が終わったら下葉の摘葉を行い、株元に太陽光線が十分当たるようにする。また、草勢が強い場合は、主枝の摘芯と同時に天葉を摘葉し草勢を調節する。
(ク)収穫が始まったら、中~上位葉を1週間に2~3枚程度の割合で摘葉する。特に子づる、孫づるの伸びに注意しながら、混みあっている部分を摘葉し、伸ばしたい枝に十分に太陽光線が当たるようにする。
(ケ)孫づるは、下位のものは1~2節で摘芯し、中~上位のものは放任とするが、勢いの強い枝は摘芯し、放任枝は3~5本位に調節する。摘芯は少しずつ行うようにする。1度にまとめて行うと、収穫の山ができて品質・収量が低くなるおそれがある。
⑦ 収穫
収穫果実の大きさは、草勢に応じて調節する。主枝の果実については、やや若穫りを行い、草勢の維持を図る。 側枝の果実は100gを基準に収穫するが、草勢や障害果の発生具合に応じて、穫る大きさを調節する。
収穫は午後になると果温が高くなり、鮮度が早く落ちるので午前中に行うようにする。
また、収穫の時に形の悪い果実を見つけたらすぐにつみとるようにする。
⑧ 生理障害とその対策
(ア)曲がり果
葉からの同化養分の転流が順調に行われなかったり、花芽分化期~発育期に何らかの影響を受けて花の素質が悪い場合に発生する。日照不足・着果過多・なりづかれ・追肥の不足や遅れ・水分不足等により草勢が低下することが原因となっている。原因を見きわめて、対策を講じる。
(イ)肩こけ果
低温下での発生が多い。特に夜温が低いと茎葉の生長が止まり、雌花の着生が増えて果実間で養分の奪い合いが起こり果実の肥大が悪くなった結果、発生がみられる。
摘果を行ったり、前夜温を若干高く保つ。
(ウ)先細り果
高温条件や草勢が強い場合に発生が多くみられる。
摘葉により草勢を抑える方法がとられる。
(エ)尻太り果
曲がり果と同様の原因で発生する。特に収穫最盛期が過ぎて草勢が低下したときに発生がみられる。摘果を行って負担を軽くする等、草勢を回復する対策を講じる。
(オ)流れ果
草勢が強すぎる場合や着果過多、なりづかれ、日照不足等による草勢の低下のどちらかの理由で同化養分がうまく果実に分配されない場合に発生がみられる。
原因を見きわめて対策を講じる。
(カ)葉やけ
4月以降、晴天で日射の強い日中はカーテンで日よけをすると葉の傷みを防ぐことができる。
⑨ 病害虫防除
(ア)べと病・灰色かび病・菌核病
3月下旬の比較的気温が高い時期に降雨が続くと加温機が稼動しない状態で湿度が高くなり発生がみられる。 送風の状態で加温機を稼動させ施設内の空気を動かして病気の発生を防ぐ。
(イ)ミナミキイロアザミウマ
紫外線カットの被覆材を使用する。ガラス温室の場合は内カーテンに紫外線カットフィルムを使用する。
(角田 巌 、那須 大城)