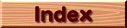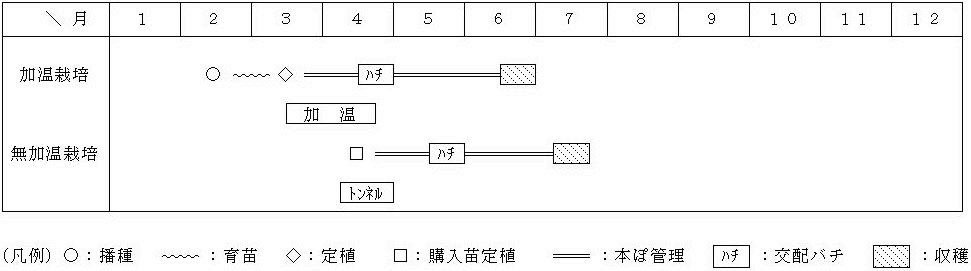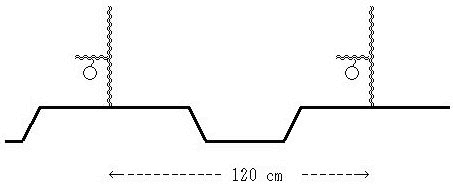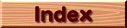

半促成メロン
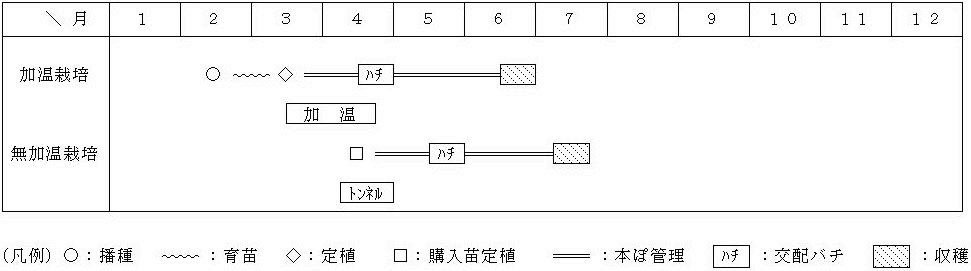
1. 品種例 アールスセイヌ
2. 目標収量 2,800 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
ほ場排水性が重要で必要に応じて暗渠を埋設する。
4. 技術内容
(1) 育苗
① は種 は種期 2月中旬
種子量 1,000㎡当たり2,400粒
(ア)は種方法
は種床にはバーミキュライトを使用するとよい。 バーミキュライトは事前に十分保水させておくこと。
条間6㎝、深さ5㎜のは種溝を切り、3㎝間隔で種子をまく。
(イ)は種後の管理
は種後は床温を30℃前後に維持し、発芽後は28℃程度に下げる。
② 鉢土の準備
田土に完熟堆肥を1:1の割合で混合する。堆肥の代わりにくん炭を混用してもよい。
速成床土作成例 (1,000リットル当たり)
材料/肥料 |
量 |
無病の田土 |
500 リットル |
完熟堆肥 |
300 リットル |
もみがらくん炭 |
200 リットル |
苦土石灰 |
1.0 kg |
過燐酸石灰 |
2.0 kg |
細粒868
|
2.5 kg
|
施肥量は床土1,000リットル当たりチッソとカリが200g、リンサンは500g施用する。
使用する1カ月以上前に調整しておく。
床土は県防除基準に基づき消毒する。臭化メチルで消毒する場合は石灰肥料の混合時期に注意する。
(ア)鉢上げとその後の管理
発芽が揃えば早めに12㎝ポットに鉢上げする。鉢上げ時の潅水はぬるま湯を用いて、株元が落ちつく程度の最 小限とする。
☆育苗中の温度管理
鉢上げ〜本葉2.5枚 気温25〜28℃、地温20〜 22℃、本葉2.5 枚以降 地温18℃前後で徐々に馴化させる。
☆苗ずらし
葉が触れ合う状態になれば鉢をずらし、徒長防止する。
(2) 本ぽ準備
① ほ場準備
ほ場は耕土が深く有機質に富んでおり排水が良いことが重要である。
畝は適湿状態にしてから定植10日前までに透明マルチを掛け、できるだけ地温を上げておく。
② 施肥例 (kg/1,000㎡)
肥料名 |
成 分 |
基 肥 |
熟成堆肥 |
|
2,000 |
苦土消石灰 |
|
150 |
骨粉 |
|
50 |
有機配合肥料 |
5-5-5 |
150 |
低度化成肥料(ほう素入り)
|
8-6-8
|
30
|
③ 畝立て、栽植密度(2,000株/1,000㎡ )
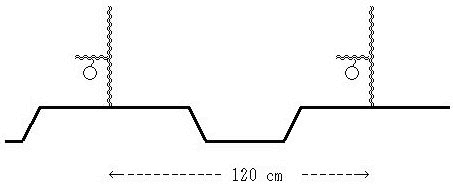
(3) 定植
畝幅120cmに1条植え、株間40cmとする。
苗は本葉 3.5枚程度とし、苗には前もって灌水し、根鉢が崩れないように定植する。定植時のかん水はぬるま湯を使用する。
定植後は速やかにトンネル被覆して保温する。
(4) 温度管理
定植後は昼間温度を28℃前後に保ち、夜間温度は13℃ 以上を確保する。
(5) 整枝
展開葉5枚頃から側枝を取り除き草勢を抑える。 主枝は展開葉17枚頃に20枚程度を残して摘芯するが 着果節位より上に本葉8枚が確保できること。
結果枝の摘芯は2節を残し摘芯するが、第1節間長15〜20㎝、第2節間長8㎝前後の時期とする。
(6) 誘引
展開葉7枚〜8枚で蔓先を揃えて誘引を始める。
(7) 摘葉
本葉5枚頃に子葉を除去し、主枝摘芯までに本葉1〜3葉を順次摘葉する。
(8) 着果節位の決定と結果枝の限定
展開葉15枚頃に畝上50〜60㎝の高さで結果枝より下に最低8枚の葉を確保できる節位(11〜15節)とし結果枝は3本を残し、他は早めに整理する。
(9) 交配ミツバチ搬入
定植後30〜35日で開花が始まるので、結果枝を観察し開花2日前頃より搬入する。また、エフを付け、開花日を必ず記録しておく。
(10)摘果と雄花除去
鶏卵大の頃、1果を残して他を摘果する。残す果実は縦径のやや長い形のものとする。また、摘果とともに雄花も早めに除去する。
(11)玉つりと袋かけ
果実の直径が7〜8㎝くらいから玉つりを始める。結果枝が着果節より下がらないよう注意する。玉つりが完了したら新聞紙で袋かけを行う。
(12)土壌水分管理
展開葉が10枚の頃から主枝摘芯期まで葉縁部に若干結露がみられる程度の水分状態を保つ。 開花前から着果まで潅水はしないこと。
果実が鶏卵大から初期肥大が始まるので、潅水を再開するが一度に多量でなく少量で潅水回数を多くする。
果実の直径が7〜8㎝から硬化が始まるので、潅水を徐々に控える。ただし、乾燥しやすいほ場は極少量の潅 水を続け、茎葉がかたくならないよう管理する。
果実の縦ネットがほぼ終了したら潅水を始める。横ネットがほぼ完了したら潅水量を徐々に減らし、草勢維持のための潅水のみとする。
(13)収穫
3月定植のもので着果後(開花後)60日、4月定植のもので着果後55〜60日で収穫する。
収穫にあたっては、収穫予定日の2〜3日前に糖度検査を行い15度を目標におく。
(14)病害虫防除
県の病害虫雑草防除基準に準じて行う。
(15)主な生理障害(原因と対策)
① 裂果
ネット発生始めと収穫直前に発生が多い。表皮の硬化が強い場合、土壌水分の急増による急激な肥大によって花痕部近くが大きく開裂する。
暗渠による排水対策など地下水位の影響を少なくする。
② 扁平果
ネット発生始めまでの肥大を抑え、後半になって急激に肥大させた場合に発生しやすい。
着果後から硬化期までの過乾燥に注意し、茎葉がかたくならないように水分管理する。
③ 苦味果
昼間の温度が高く過乾燥や窒素過多による過繁茂状態が続くと発生しやすい。
(冨永 敬二、井上 太一郎)