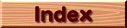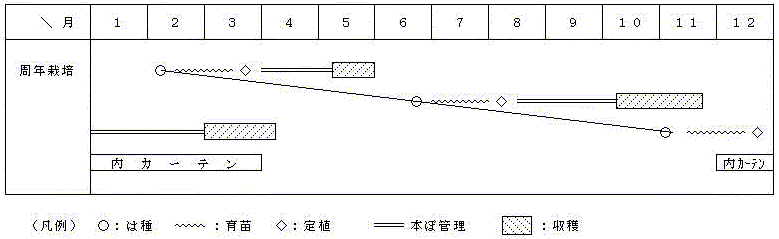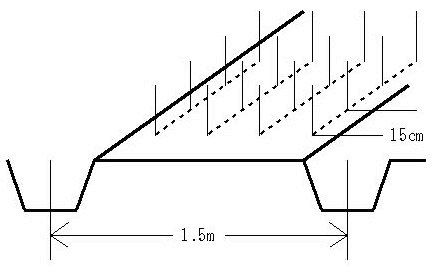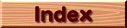

葉ネギ・細ネギ (周年栽培)
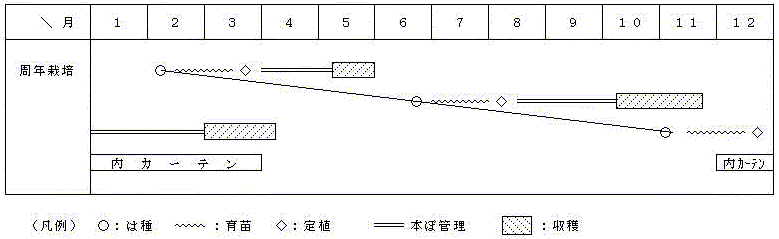
1. 品種例 葉ネギ 九条太系、九条細系、黄系九条
細ネギ 奴 など
2. 目標収量
葉ネギ 夏どり 3,000 kg/1,000㎡
秋冬どり 4,000〜5,000 kg/1,000㎡
3. 栽培のポイント
堆肥などの有機物と石灰資材を施し、十分な土づくり を行う。
乾燥には強いが、湿害に弱いので排水を徹底する。
施肥直後の播種、定植は根を傷めるのでさける。
ハウス栽培では、降雨による肥料成分の流亡が少ないため、毎作の施肥は肥料過多になる恐れがある。このため、土壌のpH、ECを測定し、施肥量を調節する。
高温多湿の温度管理をしたり、株間が狭いと、軟弱徒長し倒伏の原因となるので注意する。
4. 技術内容
(1) 育苗(葉ネギの場合)
① 育苗床の準備
本ぽ1,000㎡あたり、春まき70㎡、夏まき80㎡、
秋まき60㎡の育苗面積を用意する。
(ア)育苗床の施肥例 (10㎡あたり)
|
肥料名 |
成 分 |
基 肥 |
|
熟成堆肥 | | 30 |
|
苦土消石灰 | | 1 |
|
ようりん | | 1 |
|
低度化成肥料 |
8-6-8 | 1 |
肥料は播種の1〜2週間前までに施し、土と良くなじませておく。
(イ)畝立て
幅1.2mの平畝を作る。高さは土壌条件により調節する。
(ウ)害虫防除(虫害)
農作物病害虫防除基準に従い、粒剤を施用しておく。
② 播種
本ぽ 1,000㎡あたり1リットルの種子を準備し、平畝上に散播する。
播種後は、薄く覆土をおこない、雑草と乾燥防止を兼ね、もみがらか切りわらを施用する
③ 管理
灌水は発芽までは十分に行い、発芽後は控えめにする。
温度は15〜25℃になるよう管理する。
そろった良い苗を作るためと除草をかねて間引きを2〜3回行う。追肥は苗の生育を見て液肥で2〜3回行う。
播種後40〜60日、草丈20〜30cmが適期苗の目安である。
(2) 本ぽの準備
① 施肥例(葉ネギの場合) (kg/1,000㎡)
|
肥 料 名 |
成 分 |
基 肥 | 追
肥 |
|
熟 成 堆 肥 | |
2,000 | |
|
鶏 ふ ん | | 300 | |
|
苦土消石灰 | | 120 | |
|
よ う り ん | | 40 | |
|
高度化成肥料 |
16-10-14 | 120 | 30×1〜3回 |
細ネギの場合は元肥の高度化成肥料を100kg程度とする。
② 畝立て、裁植密度(17,000株/1,000㎡ )
畝幅150cmの平畝を立てる。4条植えで株間15cm、
1ヵ所3本植えとする。
作型により生育期間が短い場合や品種によっては十分に分げつしないことがあるため、作型、品種にあわせて植え付け本数、株間を調節する。
(3) 播種(細ねぎの場合)
本ぽ1,000㎡あたり4リットルの種子を準備する。
播種にはソワーの播種機を利用する(播種幅10cm程度)。
播種後は、発芽までの水分確保と一斉発芽をさせるため、べたがけを行う。べたがけ期間は夏期で発芽後1週間、冬期は2週間とする。
(4) 定植(葉ネギの場合)
条間30cm、溝幅10cm、深さ3〜5cm程度の植え溝を切る。植え溝に、3本ずつ、株間15cmで、できるだけ苗が直立するよう植え付ける。
土寄せは根が隠れる程度に薄く行う。
植え付ける苗にばらつきがあると、生育がそろわず品質が低下するため、苗の大きさで選別して植える等、できるだけ生育をそろえるようにする。
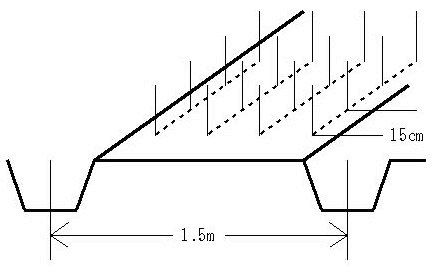
(5) 灌水
定植後は十分灌水し、活着を促進する。
灌水は頭上灌水により、夕方5時以降はさける。
ネギは過湿に弱いため、活着後は過灌水にならないように注意する。
収穫の約15日前からは、灌水を控え葉色を濃くし品質向上を図る。
(6) 追肥、中耕、土寄せ
追肥は第1回目を定植後10〜15日のうちに行う。このとき植え溝の横に浅く溝を切って施す
2回目以降の追肥は、生育、葉色の状況、収穫時期により適宜行う。
追肥施用時に、施肥効果を高め、除草、倒伏対策をかねて中耕土寄せを行う。
(7) ネットの設置(細ねぎの場合)
倒伏防止のために、編み目12cm×12cmのネットを設置 する。
(8) 収穫
草丈が60〜70cmで、茎の直径が0.8〜1.2cm(収穫時期 による)のものを目安に収穫する。収穫は早朝の低温時に行い、外皮をむいて、ていねいに調整する
(9) 病害虫防除
病害虫については次のものに注意する。
防除は農作物病害虫雑草防除基準に基づく。
① べと病
4〜5月頃、15〜20℃程度の気温で降雨が続くと発生が多い。土壌中に残った被害部が次作の伝染源となる。 連作ほ場は排水の悪いほ場で多発する。
② 黒斑病
5月頃から発生し、梅雨期や秋雨期等湿度が高い時期に多発し11月頃まで発生する。
生育後期における草勢のが衰えや葉の損傷は、発生を助長する。
③ さび病
春と秋に、比較的低温で降雨の多いときに発生が多い。 また、肥切れによる草勢の低下は発生を助長する。
④ スリップス類
夏期の高温乾燥が続くと多発する。特に雨よけ栽培で発生が多い。
⑤ ネギハモグリバエ
春〜夏にかけて発生が多い。特に5〜6月に降雨が少ないと多発する。
⑥ ネダニ
酸性土壌で発生しやすい。定植時に健全なものを選ぶ。
⑦ ネギコガ
夏に被害が多い。
⑧ シロイチモジヨトウ
5〜11月に発生し、8月下旬〜9月の被害が多い。
施設の産地が集中している場合は、フェロモン剤の効果が高い。
(10)主な生理障害
① 葉先枯れ症
原因は土壌中のCa不足、あるいは土壌pHが低いことによるCa吸収阻害等による。夏期に発生が多い。
対策としては、pH 6.0以上となるように石灰質肥料の施用ならびに深耕による下層土の改良に努める。
(野口 英明、井上 太一郎)